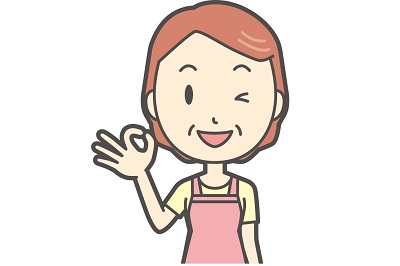
小規模企業共済は、中小機構という国の機関が運営している中小企業の経営者や役員が老後の生活資金を準備するための「経営者の退職金制度」です。
積立てしながら節税にもなり、いざという時の貸付制度もある大変メリットのある制度です。無理のない金額から積立てが出来て、節税効果もある優れた制度といえるでしょう。
現役を引退された後の安定した生活のために、ぜひ検討したい制度です。
ここでは、小規模企業共済のメリットとデメリットを説明し、注意点などもあわせてご案内いたします
スポンサーリンク
小規模企業共済とは?誰が入れて、いくらまで掛けられるの?
個人事業者や小規模企業の役員などが入れるこの制度ですが、具体的に誰がいくらまで入れるのかをご説明します。残念ながらサラリーマンは加入出来ません。
| 加入資格 | ●常時使用する従業員が20人以下(商業とサービスは5人以下)の会社役員または個人事業者 ●上記の個人事業者の事業に関わる共同経営者 |
|---|---|
| 掛金 | ●口座振替で納付する。「月払い」のほか「半年払い」「年払い」が選択できる。 ●掛金は月額で1000円?70000円までの範囲。500円単位で自由に選べる。 ●加入後、経営状況に応じて、増額・減額ができる。 |
240ヶ月以上積み立てれば返戻率は100%以上!掛金は全額が所得控除されるので、実質的な返戻率はもっと高い
事業をやめた時などに、それまで積み立てていた掛金を共済金としてまとまったお金を受け取ることができます。20年(240ヶ月)以上積み立てていれば、100%以上の返戻率となります。
小規模企業共済の掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。(掛けた金額は経費として損金扱いされる)仮に最高額の70000円を掛けている場合は、年間840000円の所得控除がされます。
また、共済金は請求事由によって受け取れる金額が異なります。
では、中小機構のHPにあるシュミレーションを使って課税所得金額300万円の企業が月30000円ずつ積み立てた場合の共済金額を見てみましょう。(注意:下記の表は平成28年10月現在の試算です)
【共済金A:事業廃止の場合の共済金】
| 掛金納付月数 | 掛金総額 | 共済金 | 実質返戻率 |
|---|---|---|---|
| 240ヶ月(20年) | 7200000円 | 8359200円 | 146% |
| 300ヶ月(25年) | 9000000円 | 10860600円 | 151% |
| 360ヶ月(30年) | 10800000円 | 13044000円 | 151% |
【共済金B:老齢給付の場合の共済金】
| 掛金納付月数 | 掛金総額 | 共済金 | 実質返戻率 |
|---|---|---|---|
| 240ヶ月(20年) | 7200000円 | 7976400円 | 139% |
| 300ヶ月(25年) | 9000000円 | 10245600円 | 143% |
| 360ヶ月(30年) | 10800000円 | 12635400円 | 147% |
もちろん試算の条件と実際の加入履歴が異なる場合は上記の試算結果にはなりませんが、この結果から事業をやめた場合に受け取れる共済金Aの返戻率が一番高いですね。
受け取り方は?受け取る時の税負担も軽くなる?
共済金Aと共済金Bについては「①一括受け取り」「②分割受け取り」の他に「一括受け取りと分割受け取りの併用」が可能です。
①の一括受け取りの場合の共済金は退職所得扱いとなり、②の分割受け取りの場合は公的年金と同じ雑所得扱いとなります。つまり、どちらの受け取り方を選んでも所得控除が受けられることになります。
小規模企業共済は、掛金を積み立てている間は節税になりますが、受け取る際は税金を払うことになります。ただし、先にも述べた通り受け取り時の税負担は大幅に軽減されるので、トータルで見ると税負担はそれほどでもないのかもしれません。
いざという時の貸付制度!手続きも簡単に貸付が受けられる
小規模企業共済には「契約者貸付制度」があります。これは納付した掛金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられる制度です。
なおその際の年率は低く、一般の金融機関からの借り入れに比べて手続きも早いです。
【契約者貸付制度】
| 借入れ限度額 | 掛金の範囲内(7割?9割)で10万円以上2000万円以内 |
|---|---|
| 年率 | 0.9%~1.5% |
| 担保・保証人 | 不要 |
デメリットは?元本割れのリスクも
節税にもなっていざという時に頼りになる小規模企業共済ですが、利用する上でのデメリットと注意点を見ていきましょう。
元本割れに注意
加入期間が20年未満で任意解約の場合は、元本割れしてしまいます!
納付期間が1年以上7年未満なら、解約手当金は掛金の80%となり、納付期間20年で掛金の100%(掛金と同額)が受け取れます。掛金以上を受け取るには20年7ヶ月以上が必要になりますので注意が必要です。
解約の際は税金に注意
任意解約の場合、受け取る金額の種類は「共済金」ではなく「解約手当金」となります。
これは「一時所得扱い」となり、控除額は少なく払う税金が多くなります。
1年未満での解約に注意
納付期間1年未満で任意解約すると掛け捨てとなり、一円も戻ってきません!掛金の全てが無駄にしないために、無理のない金額から始めるように計画しましょう。
まとめ
小規模企業共済は、サラリーマンのような退職金がない個人事業者にとって、とてもありがたい制度だと思います。
積立てで支払った掛金は全額が所得控除の対象となり、受け取る際の税負担も軽くなります。また、長期間加入することで将来もらえる金額も掛金以上になって戻ってくることもあり、大変お得な制度だと言えるでしょう。
ただし、場合によっては損をすることもありますので、制度の把握をしっかりしてから上手に活用することをお勧めします。
