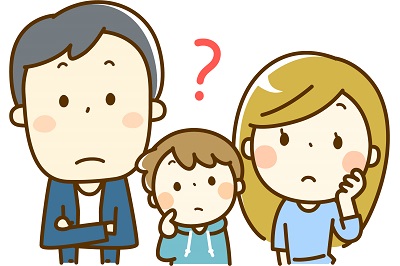
遺族厚生年金とは、会社の厚生年金に加入していた方が亡くなってしまったときに、遺された家族が受け取れる公的年金のことです。国民年金から支給される遺族基礎年金とは別に、上乗せとして受け取ることができます。
受給するための条件や給付額の計算方法などは、遺族基礎年金と比べると多少難しく感じる部分もあるかと思いますが、いざという時には家族の大きな支えとなる、非常に重要な制度です。
ここでは、受給に関する被保険者の要件から、遺族の範囲や年齢要件、順位などを、分かりやすく解説していきたいと思います。
さらには受給額の計算方法や期間、支給停止となる事由までご紹介しますので、遺族厚生年金の概要をしっかりと整理していきましょう。
スポンサーリンク
遺族厚生年金の受給要件とは
まずは、亡くなった被保険者に関する受給要件を見ていきましょう。
遺族厚生年金では保険料納付要件と死亡日要件が定められており、さらに死亡日要件には短期要件と長期要件の2種類があります。それぞれの詳細は以下の通りです。
保険料納付要件
- 保険料納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の2/3以上あること
(ただし平成38年4月までは条件が緩和され、65歳未満であれば直近1年間の保険料を滞納していなければOK)
※ここでのポイントとしては、遺族基礎年金と遺族厚生年金の保険料納付要件は共通しているため、遺族厚生年金であっても国民年金の期間で判断されるということです。
死亡日要件
【短期要件】- 厚生年金に加入している人が死亡した
- 厚生年金加入中に初診日がある傷病により5年以内に死亡した
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した
の、いずれかを満たす方
【長期要件】
- 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間が25年以上ある人が死亡した
(この場合、保険料納付要件は問われません)
※長期要件にある受給資格期間に関して、国民年金の寡婦年金では10年以上に緩和されましたが、遺族厚生年金では25年以上のままとなっていますので、ご注意ください。
短期要件と長期要件で大きく異なる点は、年金額の計算方法です。
短期要件では被保険者が加入していた期間は問わず、1月しか加入していなくても支給の対象となります。さらには最低保証として300月は加入していた、とみなして計算してもらえるのです。
しかし長期要件では300月のみなし期間がありませんので、実際の加入期間を基に計算されます。期間が短い場合には、年金額がごく少額しかないケースも起こりえるのです。
300月のみなし期間については、後ほどさらに詳しくご紹介します。
ちなみに、働きながら老齢厚生年金を受給しており、短期・長期どちらの要件も満たしている人が亡くなったときは、いずれか有利な方を選ぶことが可能です。
誰が受給できるの?遺族の範囲と順位を解説
遺族厚生年金は、原則として「厚生年金に加入していた方に生計を維持されていた遺族」が受給対象です。
子供のいない妻や夫または父母や祖父母なども受け取ることができるなど、遺族基礎年金よりも対象範囲が広がっており、その中で優先順位が設けられています。
以下の表は順位ごとの対象者と諸要件をまとめたものです。妻以外の遺族には、年齢要件がある点もチェックしておきましょう。
| 順位 | 対象者 | 要件 |
|---|---|---|
| ① | 子供 | 18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満) |
| 妻 | 年齢条件なし | |
| 夫 | 死亡日において55歳以上 | |
| ② | 父母 | 死亡日において55歳以上 |
| ③ | 孫 | 18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満) |
| ④ | 祖父母 | 55歳以上 |
ここに注意!
第1順位である夫ですが、妻の死亡日時点で55歳未満のときには、遺族厚生年金の受給権がありません。
子どもがいて、遺族基礎年金を受給している場合でも、遺族厚生年金の支給対象は夫ではなく子どもになります。
また、55歳以上60歳未満の夫では、子どもがおり遺族基礎年金を受給している場合のみ、60歳前であっても遺族厚生年金が支給されます。夫の受給に関しては、妻とは異なり細かな要件が多くなりますので、しっかりと認識しておきましょう。
遺族厚生年金はいくら貰えるのか
次に、遺族厚生年金で貰える年金額は、どのような計算に基づいて決定するのでしょうか。
遺族厚生年金では、遺族基礎年金のような一律の支給額が定められているのではなく、平均標準報酬から算出された報酬比例部分のおよそ3/4の金額です。そこに、職種や家族構成による加算額が上乗せされて、最終的な支給額が決定されます。
報酬比例部分の年金額の算出は、以下の計算式を使用します。

※引用元:遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
先述した死亡日要件で、被保険者が短期要件に該当する場合は、上記の計算式に当てはめる被保険者期間が25年(300月)未満であれば、300月としてみなして計算するという特例があります。
これにより、実際の厚生年金への加入期間にかかわらず、遺された家族がある程度まとまった年金を受け取れるように考慮されているのです。
受給例
・厚生年金加入期間:10年(120月)
・平均報酬額:35万円
のケースでは
35万円×0.5481%×300月(みなし)×3/4=43万1.629円
今回のモデルケースでは、約43万円が遺族厚生年金の額になります。
もし長期要件の場合には300月のみなし期間ではなく、120月で計算することで求められます。
300月に満たない場合は300月加入していたとみなして計算するため、一定額以上の給付を受けられる
遺族厚生年金は、実際に加入していた月数と報酬額に応じて算出されますが、短期要件に該当する方が25年未満の期間中に亡くなった場合には、300月とみなして計算する、という決め事があります。
その理由としては、まだ比較的若い世代の方が加入期間の短いうちに亡くなってしまうと、年金とは言い難いほどの少ない支給額となってしまいます。
そこで、一定額以上の年金を最低保証するために、300月に繰り上げて計算して給付しましょう、という制度なのです。
先ほど受給例として挙げた給付額の計算ですが、300月のみなし期間がなかったとして計算してみましょう。
35万円×0.5481%×120月×3/4=17万2,652円
実際に加入していた120月で算出すると、年金額は約17万円となりました。300月みなし期間で算出したときの約43万円と比べてみると歴然とした差となり、みなし期間は遺族への保障が大きく底上げされていることがわかりますね。
遺族厚生年金はいつまで貰えるのか
それぞれの遺族厚生年金の支給期間について、以下の表にまとめてみました。
| 対象者 | 受給できる期間 |
|---|---|
| 子供 | 死亡した日の翌月から18歳到達年度末まで (障害等級1・2級の場合は20歳年度末まで) |
| 妻 | 30歳未満の子のない妻は死亡した日の翌月から5年間のみ 30歳以上または子のある妻は死亡した日の翌月から一生涯支給 |
| 夫 | 60歳から開始、一生涯支給 |
| 父母 | 60歳から開始、一生涯支給 |
| 孫 | 死亡した日の翌月から18歳到達年度末まで (障害等級1・2級の場合は20歳年度末まで) |
| 祖父母 | 60歳から開始、一生涯支給 |
子どもや孫は定められた年齢に到達するまでの支給となりますが、夫・父母・祖父母では60歳から支給が開始され、要件から外れない限りは一生涯年金を受け取ることができます。
妻は年齢による要件もありませんが、要件が緩くまだ働ける若いうちから年金を受給し続けることが問題視されたこともあり、30歳未満で子どもがいない妻に関しては5年間だけの有期支給となっています。
本当に困った状況を救済するための年金、という本来の目的に沿ったルールということなのでしょう。
続いて、受給している遺族厚生年金が支給停止となる共通事由は、以下の通りです。
- 受給者が死亡したとき
- 婚姻(事実婚を含む)したとき
- 直系血族及び直系姻族以外の養子になったとき
- 離縁によって、死亡した被保険者との親族関係が終了したとき
また、遺族年金を受給しながら65歳を過ぎると、老齢年金を受給する権利が発生します。しかし基本的に「1人1年金」と決められていますので、同時に受け取ることはできません。
どちらの金額が多いかを比較して、有利な方を選択受給することとなります。
