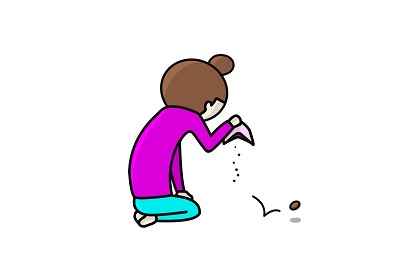
わたしたちの生活にはいろいろな経済的リスクが潜んでいます。一家の大黒柱が死亡する、障害状態になる、そんな悲劇が突然起こる可能性もありますし、十分な蓄えがないまま老後を迎える、というのも考えられるリスクです。
そんな非常事態にわたしたちの生活への経済的負担を少しでも減らすために、日本には国民全員に「国民年金」というシステムがあるのです。
国民年金の保険料は現在、16,490円/月払(平成29年現在。その年の改定率によって変動します。) この保険料を納めることで、上記のような経済的リスクに備えています。役割としては国全体で加入している保険、ということですね。
今回の記事は、この国民年金保険料を支払うことが難しくなったときの方法のひとつ「免除」についてお伝えしたいと思います。なんの対処もせずに、払えないから払わない、という状態を「未納」といいますが、未納と免除には同じ保険料を払わない状態でも大きな差があります。(このページの下の方で表にまとめています)
免除には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、さらに配偶者のDVがあった場合や失業した場合には特例があります。
免除が承認された場合の免除額と保険料のまとめは以下の表のようになります。
| 全額免除 | 免除額:16,490円 保険料:0円 |
|---|---|
| 4分の3免除 | 免除額:12,370円 保険料:4,120円 |
| 半額免除 | 免除額:8,240円 保険料:8,250円 |
| 4分の1免除 | 免除額:4,120円 保険料:12,370円 |
引用元: 日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度」
それでは詳しく見ていきましょう。
スポンサーリンク
全額免除について
全額免除とは、本来支払うべき保険料(16,490円/月)が全額免除される制度です。ポイントは2つあります。
1つ目は老後の年金受け取りについてです。
老齢基礎年金(40年納付した場合779,300円/年が65歳以降に年金として受け取れます。)を受け取るために必要な加入期間は25年間。つまり最低でも25年分の年間保険料を納めていないと老齢基礎年金は受け取れない、ということになります(平成29年8月からは10年間に変更)。
前述した「未納」の場合はこの加入期間にはカウントされないのですが、免除は加入期間として含んでいいことになっています。
2つ目は、万が一死亡や障害状態になったときに受け取る障害・遺族基礎年金についてです。
障害基礎年金(2級で約78万円/年)遺族基礎年金(子が1人ある配偶者の場合、1,003,600円/年)の支給要件には「保険料納付済み期間が3分の2以上ある、または免除されていること」という項目があります。
老齢基礎年金と同じく、「未納」は加入期間にカウントされませんが、免除は加入期間に含めることになっています。
全額免除の所得の基準
保険料が全額免除になるには所得の基準があります。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
全額免除した場合の年金額への反映
全額免除になった期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されるようになります。つまり、2分の1を国庫負担として国が負担してくれることになります。(平成21年3月分までは3分の1)
4分の3免除について
4分の3免除とは、保険料の4分の3が免除される制度です。納付する保険料は4,120円/月(29年度)になります。
全額免除と同じように、老齢基礎年金、障害・遺族基礎年金の加入期間としてカウントすることができます。
4分の3免除の所得の基準
保険料が4分の3免除になる基準は以下の通りです。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
4分の3免除した場合の年金額への反映
4分の3免除になった期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の「8分の5」が支給されるようになります。(平成21年3月分までは2分の1)
半額免除について
半額免除とは、保険料の半額が免除される制度です。納付する保険料は8,250円/月(29年度)になります。
全額免除と同じように、老齢基礎年金、障害・遺族基礎年金の加入期間としてカウントすることができます。
半額免除の所得の基準
保険料が半額免除になる基準は以下の通りです。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
半額免除した場合の年金額への反映
半額免除になった期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の「8分の6」が支給されるようになります。(平成21年3月分までは3分の2)
4分の1免除について
4分の1免除とは、保険料の4分の1が免除される制度です。納付する保険料は12,370円/月(29年度)になります。
全額免除と同じように、老齢基礎年金、障害・遺族基礎年金の加入期間としてカウントすることができます。
4分の1免除の所得の基準
保険料が4分の1免除になる基準は以下の通りです。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
4分の1免除した場合の年金額への反映
4分の1免除になった期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の「8分の7」が支給されるようになります。(平成21年3月分までは6分の5)
納付、免除・特例、未納の主な違い
納付、免除・特例、未納の主な違いをまとめると以下の表のようになります。
| 老齢基礎年金を受けるための加入期間 | 老齢基礎年金額への反映 | 障害・遺族基礎年金を受けるための加入期間 | |
|---|---|---|---|
| 納付 | ◯ 加入期間になる | ◯ 反映される年金額の全額 | ◯ 加入期間になる |
| 全額免除 | ◯ 加入期間になる | △ 反映されるが減額あり (年金額の1/2) |
◯ 加入期間になる |
| 一部免除 | ◯ 加入期間になる | △ 反映されるが減額あり (年金額の5/8~7/8) |
◯ 加入期間になる |
| 学生納付特例 | ◯ 加入期間になる | × 反映されない 0円 |
◯ 加入期間になる |
| 未納 | × 加入期間にならない 0円 |
× 加入期間にならない 0円 |
× 加入期間にならない |
参照元: ナツメ社「図解 いちばん親切な年金の本 17-18年版」
離職票を持って行くと前年所得が0になる
失業した年、またはその翌年に申請された場合に適用される制度で、「退職(失業)による特例免除」といいます。
この特例免除を使うと、退職(失業)した本人の前年所得を除外して免除基準の審査を行います。つまり、本来は
・退職者本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得
ですが、退職(失業)者特例免除では、
・配偶者の所得+世帯主の所得
のみで審査に臨むことになります。
この退職(失業)による特例免除に該当する期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金の支給期間にも含まれますし、将来の老齢基礎年金の年金額にも一部反映されます。
手続きには、退職(失業)の事実があることを示す必要があるので、離職票(その他失業していることがわかる公的期間の証明の写し)と国民年金手帳を持参し、住民票のある市区町村役場に「国民年金保険料 免除申請書」を提出することで審査されます。
国民年金保険料の申請方法
申請先は住民登録のある市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。窓口に必ず提出が必要な書類は次の2点です。
・保険料免除の申請書(窓口に備え付けのもの、もしくは日本年金機構HPよりダウンロード)
・国民年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
上記の他にも、所得に関する書類や、特例を受ける場合だとそれを証明する書類が追加で必要になる場合もあります。必要書類や手続きに関してはお近くの年金事務所にご確認ください。
