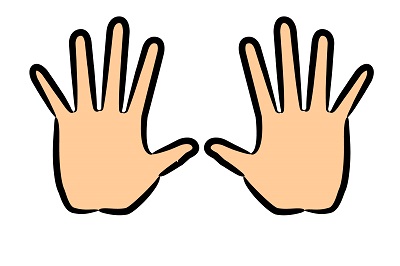
国民年金が未納になっている方はぜひ知っておいて欲しいのですが、日本の年金制度には申請をして一定の条件を満たすことで「国民年金保険料の免除」や「納付猶予」という選択肢を取ることが出来るのです。
このページでは主に納付猶予について解説しています(免除の詳細はこちらのページへ)。
保険料を支払うことが難しいときは、この納付猶予の手続きをとることで、未納の期間を作ってしまうデメリットを軽減することができます。デメリットとは、①障害・遺族年金の受給ができなくなる可能性があること、②追納できる期間が2年しかないこと、の2つです。
猶予には、20歳から50歳までが対象の「納付猶予」と、大学、専門学校などに在学している学生が申請する「学生納付特例」の2種類があります。所得の条件や申請方法も異なります。
猶予と免除の違い
日本の年金制度には、経済状況や社会環境が変化してもきちんと制度が保たれるためのたくさんの仕組みがあります。
そのなかの一つが、国民年金の保険料を納めることが難しいときの救済措置で、国民年金の保険料を「全額免除」「一部免除」「納付猶予」「学生納付特例」の制度を使うことで保険料の負担を軽減させることができる、というものです。
まず、以下の表をごらんください。
| 老齢基礎年金を受けるための加入期間 | 老齢基礎年金額への反映 | 障害・遺族基礎年金を受けるための加入期間 | |
|---|---|---|---|
| 納付 | ◯ 加入期間になる | ◯ 反映される年金額の全額 | ◯ 加入期間になる |
| 全額免除 | ◯ 加入期間になる | △ 反映されるが減額あり (年金額の1/2) |
◯ 加入期間になる |
| 一部免除 | ◯ 加入期間になる | △ 反映されるが減額あり (年金額の5/8~7/8) |
◯ 加入期間になる |
| 納付猶予例 | ◯ 加入期間になる | × 反映されない 0円 |
◯ 加入期間になる |
| 学生納付特例 | ◯ 加入期間になる | × 反映されない 0円 |
◯ 加入期間になる |
| 未納 | × 加入期間にならない 0円 |
× 加入期間にならない 0円 |
× 加入期間にならない |
参照元: ナツメ社「図解 いちばん親切な年金の本 17-18年版」
上記の通り、保険料を納める「納付」と、納付せず、何の申請もしない「未納」の間には「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の3つの方法があります。
この3つの制度は老齢基礎年金を受け取る際の加入期間としても、障害・遺族年金を受けるための加入期間としてもカウントされます。免除と猶予の異なる点は、免除は老齢基礎年金額に反映されるが、納付猶予と学生納付特例は反映されないという点と、前年所得の範囲が世帯全体か否かという点の2つです。
免除についてはこちらの記事に詳しい説明がありますので参考にしていただけると嬉しいです。
では、今回は納付猶予について詳しくみていきましょう!
納付猶予制度の詳細
納付猶予は、20歳から50歳未満の方で前年の本人・配偶者、各々の所得が一定額以下の場合に、審査に通ると保険料の納付が猶予される制度です。
納付猶予制度の所得の条件
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である必要があります。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例)父が世帯主、専業主婦の母、5歳長女の3人世帯だと、
(2+1)×35万円+22万円=127万円 です。
申請方法
申請は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口で、郵送も可能です。国民年金手帳を忘れずに持参しましょう。
学生納付特例の詳細
日本では20歳以上になると国民年金の被保険者になり、保険料を支払うことが義務付けられています。しかし、大学、専門学校などに在籍中のうちは学業もあり、保険料を捻出することが難しくなることが多いため「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例の所得の条件
まず、条件の前に確認しておきたいのが「所得は収入ではない」ということです。
収入から経費とみなされる分を差し引いたものが所得であり、アルバイトなどの給与所得者にも必要経費分として65万円の給与所得控除があります。
つまり、アルバイトの給与が年間65万円を超えなければ所得はゼロということで「学生納付特例制度」を利用できます。
65万円を超える、という方は以下の所得条件を満たせば「学生納付特例制度」を利用できます。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生の場合、ほとんどにおいて扶養している家族(配偶者や子供)はいないでしょうし、社会保険料(健康保険料や雇用保険料のこと)を払っている人はいないでしょうから、一般的な学生さんであれば所得が118万円以下であれば所得条件を満たすことになります。(ちなみに、給与収入で計る場合は年収194万円以下が目安となります)
この所得は学生本人のみで計算し、家族の所得は含みません。
申請方法
住民登録のある市区町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所でも受け付けていますが、在籍している学校に学生納付特例事務法人が設置されていれば学校に申請を委託することができます。
申請の際は、国民年金手帳と学生証を忘れずに持っていきましょう。
未納・滞納にするなら猶予制度を利用した方がお得
保険料を納めないまま2年が経過すると「未納」となります。後々保険料を支払う余裕ができた場合は後納制度(平成30年9月30日までは5年前まで遡って保険料を納付できる)を利用することが出来ますが、この期間を過ぎてしまうと後納として払うことが出来なくなります。
未納期間ができてしまうことには2つのデメリットがあります。
1つ目は、障害・遺族年金を受け取る資格を失くしてしまう可能性があるということです。事故などで障害2級の状態になり、働くことができなくなった場合を考えてみましょう。
きちんと保険料を納める、もしくは猶予の手続きを取っていれば、年間約78万円の障害年金を受け取ることができます。
対して、保険料を納める余裕がないから納めない、猶予の申請もせずに、未納期間が加入期間の3分の1以上になっている状態で障害2級の状態になっても障害年金を受け取れない可能性があります。これが一つ目のデメリットです。
2つ目は、老後もらえる年金額が減ってしまう可能性があるということです。
猶予も未納も年金額に反映されないという点では同じです。保険料を後から納めることを「追納」と言いますが、この追納できる期間が未納は2年しかない(平成30年9月30日までは5年前まで遡って後納できる)のです。猶予の手続きをとれば、この追納できる期間を10年に伸ばすことができます。
未納と猶予では保障の面でも将来の年金の面でもリスクが上がってしまうということです。保険料を納めるのが困難なときは、お近くの年金事務所へ相談にいきましょう。
| 未納 | 猶予 | |
|---|---|---|
| 障害年金、 遺族年金は? |
前々月までのうち3分の1以上未納があると受け取れない | 年間約78万円(障害2級)受け取れる |
| 後からでも納められる? | 2年経つと納められなくなる (平成30年9月30日までは5年前まで遡って後納できる) |
10年以内なら後から納められる |
